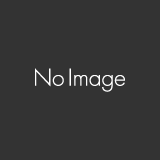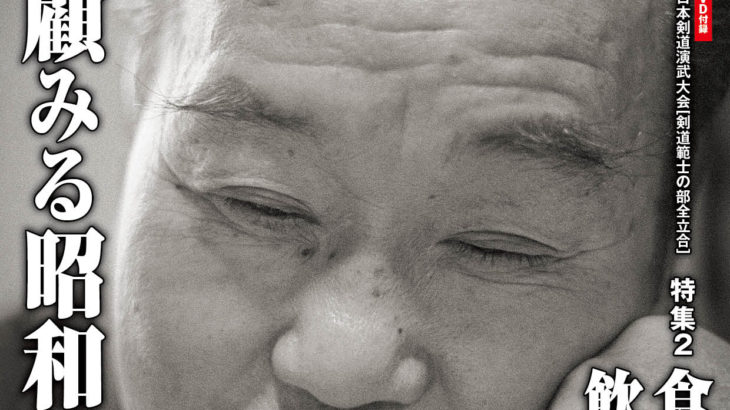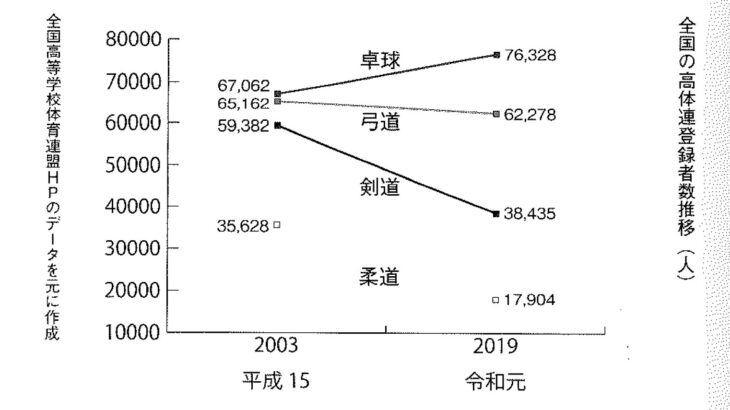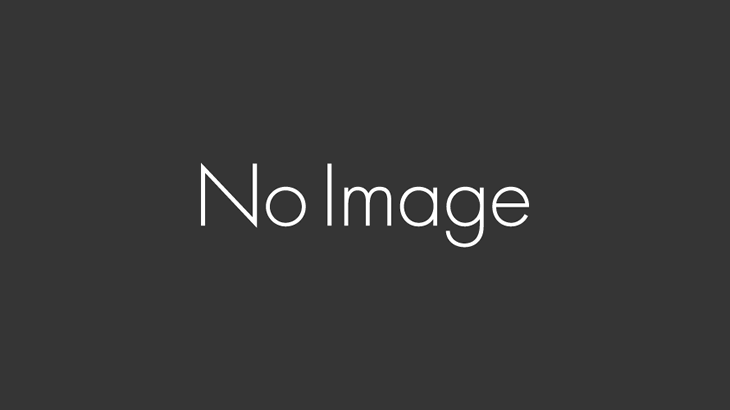「教えることは、教わること」
目黒祐樹インタビュー
―「剣道日本」7月号より―
取材・文=時見宗和
写真=川村典幸
『武蔵―むさし―(監督・三上康雄)』において、日本映画史上初めて武将、沢村大学を演じた目黒祐樹。終盤、物語の密度を一気に引き上げ、すべての視線を吸いこむ、深く雄弁な約四秒間の沈黙。「高ぶりすぎてしまったのか、クランクイン一カ月前、疲れ果ててぐったりしてしまいまして」。長く日本の時代劇を背負いつづけてきた名優の小宇宙を垣間見る。

目黒祐樹 / Yūki Meguro
昭和22年(1947)8月15日生まれ。東京都出身。6歳で子役として映画デビュー。東映初の連続テレビ映画『風小僧』の主演を最後に学業に専心。同志社中学、高校に入学し、その後、米国のハワイ州セントルイス高等学校に転校し、同校を卒業。マサチューセッツ州ボストン大学演劇学科に入学し、4年半の留学生活を終え帰国。以後、本格的に芸能活動を開始し、時代劇、現代劇を問わず数多くの映画、テレビ、舞台に出演。1980 年公開ハリウッド作品『将軍 SHOGUN』ではエミー賞最優秀助演男優賞にノミネートされる。
演じる
一九四七年八月一五日、ふたり兄弟の次男として東京に生まれた。父親はダイナミックな殺陣と軽妙な演技で人気を博した近衛十四郎。母親も時代劇の世界で活躍した水川八重子。
物心がついたころから、生活のなかに映画があった。撮影所を遊び場に育った。
六歳。兄、松方弘樹よりも早く、銀幕の世界に踏み込んだ。最初に出演した作品は『やくざ狼』。大江戸を舞台に繰り広げられる時代劇。「主役は大スター、嵐寛寿郎さんでその子どもの役という、めぐまれたデビューでした」
以後、毎年、三~四作に出演。東映が制作した初の連続テレビ時代劇『風小僧』の主役を最後に映画から離れることを決めた。一二歳だった。
「いつかまたもどろうという考えは、まったくありませんでした。映画の世界から離れた理由は大きくふたつあります。ひとつは周囲との距離感が微妙になったこと。映画やテレビに出ている人間が、学校にいる。そういう状況が、友だちもぼくも気持ちが悪くなった。いわゆる、浮いている状態になりつつあって、これは良くない、ふつうにみんなと付き合えるようになりたい。そう思ったことです。もうひとつは、子役がむずかしく、おとなの役には及ばない、だれもが通る年齢に差しかかったことです」
「アメリカに約四年半、留学させてもらいました。芸能界に未練はまったくなかったのですが、ふと気づくと、時間さえあればジャンル、B級、C級、D級を問わず映画を見ている自分がいて、次第に、ああ、やっぱりこの道が好きなんだな、この体には父親から受け継いだ血が流れているんだなと思うようになりました」
「日本という国、日本人としての心の持ち方など、外側から見たからこそ気づくこと、確認できたことがたくさんありました。アメリカでの日々は楽しくて、興味深いことはたくさんあったのですが、時間が経つにつれて、日本への思いがどんどん大きくなっていきました」
「時折、時代劇が公開されると、入場者の入替がない時代だったので、一日中映画館に入り浸りになりました。父や兄が出ていると、少しホームシックを感じながら繰り返し、繰り返し見ました。そういうなかで、映画界、とくに時代劇に対する思いがつよくなって、日本に帰ることを決めたのだと思います」
「時代劇の時代とわたしたちの時代は途切れることなくつながっています。いま、わたしたちがいる場所とはべつの時空に浮かんでいるわけではありません。もし沢村大学が生きていれば、武蔵とともに生きた時代の話しを、四五八歳の口から直接聞くことができるのですが、残念ながらそれはかないません」

「沢村大学本人に代わって、あの時代を語るのが『武蔵─むさし─』であり、広くは時代劇です。時代劇の世界はシンプルで、ひととひとが直接向き合い、関わり合っています。インターネットが発達した現代のような複雑さはありません。そこに時代劇の魅力、意味があるのだと思います」
「時代劇を見るということは、人間を見ることであり、すなわちわたしたちを見ることです。現代劇では成し得ない、シンプルだからこその深さを、演じる上で意識しなければならないと思っています」
「やった! いい演技ができた! と感じたことは一度も、ワンカットもありません。いつも、残るのはもっとできたはずだという気持ちだけです。わたしにとって、演技するということは、終わりのない戦いであり、苦しみであり、永久に一〇〇点満点を取ることのできないテストを受けつづけているようなものです。一度でいいから、達成感や満足感を味わってみたいと思いますが、もしそうなると足が止まってしまうような気もします」
「ひとつひとつ突き詰めてやっているつもりですが、進歩していないし、上達していないと感じています。今回の『武蔵─むさし─』も、あの時点での精いっぱいでしたが、振り返ってみれば、もっとああいうことができたんじゃないか、もっとこういう勉強もするべきだったなと反省点ばかりでした。自分には才能はないのかもしれない、魅力がないのかもしれない、根性が足りないのかもしれないと、いろいろ頭をよぎりますが、やめようと思ったことはありません。反省の塊のような人間ですがあきらめが悪いんです」
「映画好きで、年間五、六〇本見ています。どの映画を見ても、自分より上のひとばかり。こういう演じ方があるのか、こっちの演技のほうがわたしよりすぐれているなと、と落ちこんでばかり。そんな楽しくなかったら見なければいいじゃないかと思うんですけど、でも、好きだから見てしまう」
創る

日本映画において、目黒によって初めて演じられた沢村大学。
一五六〇年生まれ、関ヶ原の戦い、七三歳で出陣した島原の乱をはじめ、三〇回余り出陣し、九一年間の人生を全うした武将。
細川忠興につかえ、数々の軍功をたてたが、忠興は沢村よりも二二歳若い長岡興長を筆頭家老に引き上げ、沢村に言った。
「無骨者に、いままでの役目、ご苦労であった」
約四秒後、沢村は口を開いた。「はっ」
武から才知へ。時代のうねりが凝縮された四秒間の沈黙であり、表情だった。
「もう刀や槍を振りまわす時代ではない。これからは頭で時代を切り開く時代なのだ。そう思い知らされる場面ですが、沢村に限らず、すべての武人にとってのターニングポイントが、あの瞬間に凝縮されていたのではないかと思います」
「武人であり、兵法者であり、文人でもあった沢村大学。武蔵とも小次郎ともこころは通じ合っていた。非常に純粋に気高く生きてきたひとで、なぜいままでクローズアップされることがなかったのか不思議に思えるほど魅力的な人物です」
「武蔵や小次郎はよく名前を知られていますが、沢村はまったく真っ白。物語をつないでいく役割を頂いたとは思いましたが、どう演じればいいのか、最初は途方に暮れました。こういう場面を前にしたとき、沢村はどう考え、どう行動するだろう。三上監督といろいろお話をさせていただくなかで、少しずつイメージを立ち上げていきました。この頃は撮影に入る前に、監督と作品あるいは役について時間をかけて綿密に打ち合わせをする時間的な余裕がないことが多いのですが、三上監督とは、ほんとうによく話をさせていただきました。作品の第一稿も最初に読ませていただきました」
「前作の『蠢動─しゅんどう─』(二〇一三年一〇月一九日公開)が終わった後『またいっしょにやりましょう』と言われ、月に少なくとも二回、最近見た映画の話しから始まり、『武蔵─むさし─』についてのさまざまなことについて、最低一時間は話しました。『目黒さん、大根をつくってくれる農家を見つけたんですよ』『それはすごい』。劇中、武蔵が畑に飛びこんで大根を引き抜いてかじりつくシーンがあるのですが、当然、いま手に入る大根ではない。現代の大根でも判別がつかないと思うのですが、京野菜をつくっている特別な農家に頼んで、当時の品種に近いものを再現してもらうことになったというのです。監督の熱意にほだされたのでしょうね。大根だけで一五分は話したと思います」
「『俳優さんたちの疑問や質問に即座に答えることが自分の役割だ』。そう明言されているとおり、三上監督はわずかな迷いも見せません。『彼は、どうしてここでこういうセリフを口にするのでしょうか?』『後々のこのシーン、こことつながっているんです』『ああ、そういうことだったんですね』『ここでこういうセリフが出てきても不思議じゃないでしょう?』。自分で調べ、自分で書いているから、すべてが頭のなかにある。だれかが書いた作品の演出だけを手がけている監督は、そうはいかないこともあります。『ちょっと待って』と考えこまれると、役者も迷子になってしまうものです」

「役者は、だれもが同じ場、同じ高さにいます。年齢や経験は関係ありません。舞台も同じ、みんな同じ板の上にいます。だれかがだれかを引き上げる、教えるという感覚はありません。たいせつなのは、それぞれの気持ちをひとつにすること、作品をより良質にするための努力を惜しまないことです。作品の仕上がりは、役者に還元されます。質が上がっていけば、役者ひとりひとりが、普段よりも輝き、力を発揮しているように見えるようになるものです」
「撮影現場の雰囲気はさまざまです。緩んでいたり、淀んでいたりする現場もありますが、武蔵の撮影現場は、その対極でした。雑談もなく、緊張感に満ち、空気がとても澄んでいて、わたしにはとてもやりやすい現場でした」
「役者は、たとえ主役ではなくても自分が演じる役をメインに台本を読むものです。自分を中心に映画全体のイメージを、膨らませますが、監督はそうではありません。武蔵、小次郎、沢村大学、吉岡一門をはじめ、登場人物をテーブルに乗せて俯瞰します。ひとりひとりを有機的に関わり合わせながら、ひとつの物語に仕上げていきます。どんなにすばらしい演技でも、上から見たとき、物語のなかで機能していない場合、浮いている場合は、カットしなければなりません。ある種の非情さと、冷静な判断力が監督には求められます」
「教えるということは、教え子から教わること、教えること以上の教師はいないのではないかと思います。現場をまとめる立場に立って、自分の目線を一段高いところに持っていくことができたら、アメリカから日本を見たように、いままで見えなかったことが、いろいろ見えてくるのではないか。自分のなかで、変わるものがあるのではないかと思っています」 「役者なら、だれしも一度は監督をやってみたいと思うものだと思いますが、わたしにとっても夢のひとつです。一度でも、プレイヤーをすべてコントロールできる立場に立つことができたら、俳優としてもちがう面を持てるのではないかと感じます。残念ながら、これまでそういう経験をすることができなかったので、未だこのようによちよち歩いていますけれど、でも、まだ、チャンスはあるかもしれない。そう思っています」
求める

〈試合のこと、わしなりに。
まず、巌流の虎切り、別名つばめ返し。
初手は上段。
――刀が風を切る。ビュッ
切り上げ。
――ビュッ
巌流はこの動きを一瞬に。
──ビュッ、ビュッ〉
『武蔵─むさし─』の後半、武蔵と巌流(小次郎)の試合の展開と成り行きをシミュレートする沢村大学。
物語の密度が一気に引き上げられるこのシーン。どちらが勝つのか長岡興長に聞かれ、沢村は言う。
〈いま、推し量るなら、互角。勝ち負けは……。
しかし、かならず決します。
それは、試合の日まで。
いや、試合の最中に己の技以上のものを、一瞬、心と体が極めたとき〉
約四分間に及ぶカットを取り終えると、監督の三上康雄が目黒に聞いた。
「オーケーですが、どうしますか?」
このシーンのために、一年以上前から準備を重ねてきた目黒は言った。
「もう一回お願いできますか?」
巌流の初手を十字で受けて右に払い落とし、真っ向に打つところで「ずれたような気がした」からだった。
映像を確認すると、たしかに、ほんのわずか、当事者でなければ気づかないほどのずれがあった。
三上は言った。
「わかりました。もう一度やりましょう」
「長く時代劇に携わってきて、何百回、何千回と刀を振ってきました。心情は怒り、憎しみ、正義、やむを得ず、など、さまざまでした。役の気持ちに添って、相手に対するようにしてきましたが、あのとき沢村の中にあったのは、武蔵と巌流への武人としての、純粋な共感だったのだと思います」
「テレビとかの時代劇に出るときは、だいたいにおいて竹光を使いますが、今回は、本物と同じ重さの模擬刀を、あのシーンはもちろん、ふだん差している場面でも使っていました。撮影の一年以上前に、監督が、メインキャストの役柄に応じて大小、二セットずつ準備。わたしは、直接手渡されました」
「最初、左手で小刀を振れませんでした。“受ける”“払う”が定まらない。いろいろやっているうちに、腱鞘炎の気配を感じたので、素振りからやり直すことにしました。数カ月後、必要な筋肉がついて、刀をある程度振れるようになってから道場に行き、監督から送られてきたイメージビデオを見ながら、殺陣師の先生と、動きをつくり上げていきました」
「それまで刀を振る音は、効果音の世界のできごとでしたが、道場で実際と同じ重さの刀を振るところを目の当たりにすると、まったくちがっていました。力まかせに振りまわすのではなく、わずかなストロークなのに、深く、重く、だけどスピード感のある風切り音が聞こえる。これが本物なのかと圧倒されました。見よう見まねで振り始めたころは、まったく音がしませんでしたが、しばらくして、ほんの少しだけですが、風を切る音が聞こえたときは、ぞくりとしました」
約二時間に及んだインタビューの間、たたずまいの穏やかさは髪の毛一本ほども乱れなかった。回答は、つねに起承転結でていねいに組み立てられ、ひとつの物語を形づくっていた。
「長く生きてきて、いろいろな方とお会いしてきましたが、最近、改めて思うのは、ほんとうに偉い方は、まったく偉そうに見えないということです。こんなに偉い方が、どうしてこんなにふつうに、穏やかに接してくれるのだろうと、そのたたずまいに圧倒される。逆に偉そうに振る舞っている方は、じっさいのところ、看板に偽りがあることが多いですよね」

椅子から立ち上がりながら、長く時代劇を支え、背負いつづけてきた名優は言った。
「今回、縁があって『剣道日本』を素人なりに読ませていただきましたが、偉い偉くないということを超えた次元に到達なさっている方ばかり。言葉が真実を語っていて、平易なのに重い。そういう方が、さりげなく、にこやかに写っていらっしゃる。面と向かったら、なにもされなくても、威圧されて、後ずさりしてしまうんだろうなと感じました。ぼくには一生達せられない、達することのできない境地ですが、そういう世界に触れる、言葉を目にするだけでも、ああ、これは勉強になるなとページをめくりながら感じました。五〇年前にもどれたら、ぜひとも剣道をやりたい。遅まきながらそう思っています」
ひと呼吸おいて。
「剣道の試合、一度、見せていただくことはできますか?」