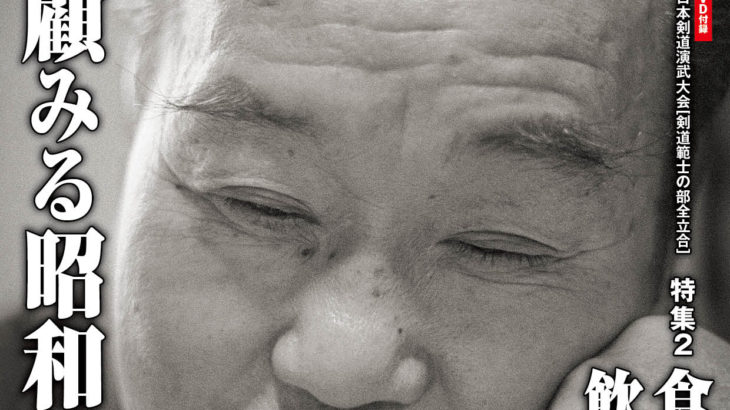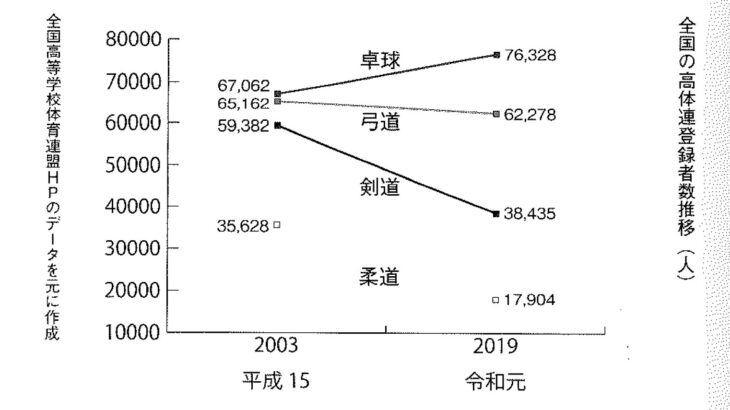映画『武蔵―むさし―』(5月25日より全国上映中) 三上康雄 監督 独占インタビュー(前編)
―「剣道日本」6月号より―

5月25日公開となる映画『武蔵─むさし─』。そのマスコミ向け試写会の壇上で、製作・脚本・監督・編集等いっさいを手掛けた三上康雄監督がこう話した。
「佐々木小次郎を紅顔の美少年とする説もあるが、ぼくは細川家に士官したほどであるならば、相応の歳は重ねていたはずだと思う」史実を精査し、登場人物一人ひとりに血肉を通わせ、随所に伏線を張り巡らせた作品は、真に迫る数々の戦闘シーンとあいまって、痛快かつ哲学的に観る側の魂をゆさぶってくる。
映画人であり、剣道経験者でもある三上監督に話を聞いた。

三上康雄 / Yasuo MIKAMI
昭和33年(1958)1月大阪市生まれ。高校時代から映画を撮り始め、24歳の頃まで16mm作品を含む自主映画を5本監督。“関西自主映画界の雄”と称されるも、その後は家業のミカミ工業に30年専念。創業百年を期に、後継者不在のため自社の株式をM&Aで譲渡し、平成24年に株式会社三上康雄事務所を設立。翌年、劇場用映画『蠢動─しゅんどう─』を監督し、全国85館で公開され、日本映画監督協会新人賞にノミネートされる。昨年、劇場用映画第二作『武蔵─むさし─』を監督し、本年5月25日にロードショー。2作品とも、製作・脚本・編集等も兼任。自身、中学から大学まで剣道に打ち込み、近年は武術、居合、殺陣に取り組む。
──例えば、武蔵と吉岡一門の一乗寺下り松での戦闘シーン。武蔵が相手のふところに刀を当て、数歩押し込んでから刀を引いて斬るという場面にもリアリティを感じました。刃で押しただけでは斬れない。抜きざまに刀を引いて相手を斃(たお)す、と。
三上 抜いて血が吹いてましたでしょ。刀に血肉がついたままでは斬れなくなりますから、武蔵はとっさに着物の袖で刀を拭っているんですよ。
──見落としていました……。刀に精通してこその描写ですね。
三上 そうですね。ぼく自身が剣道に取り組んだ時期がありますし、殺陣(たて)、居合、武術を学んできましたから、細かい疑問が次々と頭に浮かんでくる。表現するためには、しっかりと自分の腑に落とし込まなければ撮ることができないですから。
──なるほど。そんな三上康雄監督に、剣道への思い、映画監督としての思い、作品への思いをおうかがいしたいと思います。
グランドチャンピオン小次郎に挑む不屈のチャレンジャー武蔵
三上 剣道を始めたのは、それこそ武蔵のようなもので“強くなりたい”の思いがきっかけでした。空手、柔道、剣道を選択肢として一番惹かれたのが剣道で、始めたのは中学から。大学の半ばまで続けましたが、ぼくは剣道をやっていたからこの映画を作れたと思っているんです。
──と言いますと。
三上 技の習得や体づくりといった面も活きているかも知れませんが、何よりも、礼儀礼節といったことをきちんと叩き込まれたことが財産と感じます。“信義”という部分ですね。それが、この映画界に入って、いかに大切なものであるかを痛感しました。
──信義ですか。
三上 映画業界は、往々にして口約束で物事が進んでいきます。お互いを信じ合うことを大前提にしていて、契約書を交わさないことも多いんです。そのかわり、信義を破った場合は、「もうこの関係は二度とないよ」と。ぼくは年齢がいってからこの映画業界に入りましたから、最初は書面もなしに進む世界に驚いた。けれども、続けていくうちに、信義さえきちんと守れば、大物の役者さんであろうと誰であろうと、人間としてお付き合いをしてもらえるということが分かった。逆に言えるのは、信義の世界を知らない人、礼儀礼節を知らない人は、人間関係で成り立っていく世界ではやっていけないだろうということです。だから、ぼくが剣道をやっていて良かったと思うのは、技や体以上に心の問題をきちんと学べたことだと感じるんです。
──なるほど。
三上 ましてや自分は、今回の作品ではプロデューサーであり、監督であり、脚本も編集もキャスティングも全部手がけてきましたから、トップとして、牽引者として、すべてに対する気づかいや心配りができるかどうかも問われました。そこにも信義があります。それとともに、ブレずに一本筋の通った指示ができるかどうか。問われるところの答えは、すべてにおいて剣の精神と一緒だと思うんです。
──剣道が社会生活にも生きる、と。
三上 それが実感です。だから、いま剣道をやっている若い人たちも、稽古はしんどいかも知れないけれども、薄っぺらく生きていくんじゃなく、剣道のすべてが自分の身となり心となると信じて、やり続けて欲しいと思いますね。そうして社会に出て、太く生きていって欲しい。
──いい話ですね。かつての武家社会では、口約束こそがもっとも大事にされたと聞きます。
三上 そのようですね。武士の「斬る」という世界から剣道の「打つ」ということになった時点で、スポーツの要素が入りました。でも、剣の道における心の部分は、核として昔もいまも変わらぬものであるはずです。その核の部分を自分のものにしていくことが、若い人たちにとって大事なことじゃないかと思いますね。

──殺陣や居合や武術を学ばれたのは、映画のために?
三上 そうですね。前作『蠢動─しゅんどう─』を撮る前ですから、もう8年ほど経ちます。
──同じく時代劇の『蠢動─しゅんどう─』もファンの多い作品で、海外(12カ国)でも絶賛されました。それ以前にいろいろ習い始められたと。
三上 宣伝ありがとうございます(笑)。剣道はいま言ったように「打つ」ですから、「斬り方」を学ばないといけないでしょう。殺陣ではいかに格好よく斬るか、演じるか、見せ方を学びました。居合は形や太刀筋を学ぶ上で必要。武術はリアルさという点で不可欠です。それらをひと通り学ばないと時代劇は撮れないと思い、それぞれを学びました。
──今作にも、それぞれが反映されているのですか?
三上 もちろん。どうやったら勝てるか、ということをリアルに求めていきましたからね。武術の先生にも、「こういうシチュエーションなら、先生でしたらどう闘いますか?」とうかがったり。最終的には先生に出演してもらい、動画を撮り、それを出演者に見ていただきました。
──“史実に基づいた武蔵”とうたっているだけあって、戦闘シーンにしてもリアリティがありました。
三上 あると思いますよ。映画のために、どうやったら勝てるか──そればかりを真剣に考えましたから。基本は孫子の兵法じゃないけれど、一対一。映画でも、武蔵みずから竹藪に入り、吉岡勢の人数を間引きしながら戦うシーンがあります。藪の中では一対一。また、あの前のシーンでは、彼は太刀を切って、長い脇差を作る。藪での闘いがたまたま起こるのではなく、そこにも武蔵の用意周到さを描いたんです。
──冒頭、父親に鍛えられた場面が、その後に展開する武蔵の卓越した感覚や身体能力の高さをうかがわせました。
三上 父の無二斎ともめているとき、武蔵が噛んでいるじゃないですか。で、宍戸との闘いのときにも、噛むシーンがありますでしょ。同じく父親が投げつける残月(折れた刀の先)を、彼は回転して避け、一乗寺下り松のときにも、多勢が来たときに回転するシーンがある。細かく伏線は張っているんですよ。
──もう一度観たいですね。
三上 ぼくの映画は、基本的に一度観て分かる映画じゃないと思っているんです。それだけ、いろいろなところに伏線を張っている。見直すことによる発見があったり。そういう発見って観る人にとっては嬉しいじゃないですか。

──なるほどと感じたのは、試写会での監督のひと言でした。「士官までした佐々木小次郎が紅顔の美少年であったはずがない」と。
三上 はい。いろいろ調べ上げてそう思うに至り、ぼくのイメージでは松平健さんがピッタリでした。最強であり、最高の人格者である佐々木小次郎役。映画ですからエンターテイメントの部分も必要です。その意味では、グランドチャンピオンに挑むチャレンジャーの武蔵という図式こそが面白い。武蔵は一戦一戦勝ち抜いていくことによって、ついにグランドチャンピオンに挑むことができる、というね。
──グランドチャンピオンの側のストーリーもしっかり描かれていました。
三上 そうですね。登場人物のすべてに血肉を通わせたいというのもありますし、史実に基づくとはいえ、ぼくとしては武蔵の伝記に焦点をあてたかったわけではなく、あの時代の、わずか数年のあいだに起きる武蔵を巡る多層的な事象に興味があった。当然、武蔵だけでなく、一人ひとりの人物の心情にも、自然に思いが馳せるわけです。
──形稽古のシーンは、小次郎の強さを際立たせたように感じました。現代の剣道形のはるか先をいくようで、引き込まれましたね。
三上 二手ぐらいを形どおりで来て、そこから先は、「そんな形だけのものは俺は打ち破れる」というのを見せた。形は本来は打ち破れるもの。ここにも後半への伏線を張っています。
──クライマックスの巌流島の話もよろしいですか? 最後の殺陣も、あらかじめイメージは固まっていた?
三上 固まっていました。
──一瞬でした。
三上 最後に互いが高まり合ってからの一瞬ですね。剣道の試合も一緒じゃないですか。ぼくの映画では、まず場所の取り合いがあるでしょ。そこから始まって、最後に高まり合ってからは一瞬。それこそ一瞬に至るまでの伏線は無数に張り巡らしていますが……あまり言ってしまうとネタバレになってしまいますね(笑)。まあ、小次郎の燕返しが二手であることを武蔵も知っている。いざ決戦のとき、小次郎は燕返し以上の技を発揮するのか、武蔵の臨機応変が凌ぐのか──ぐらいでご勘弁を(笑)。